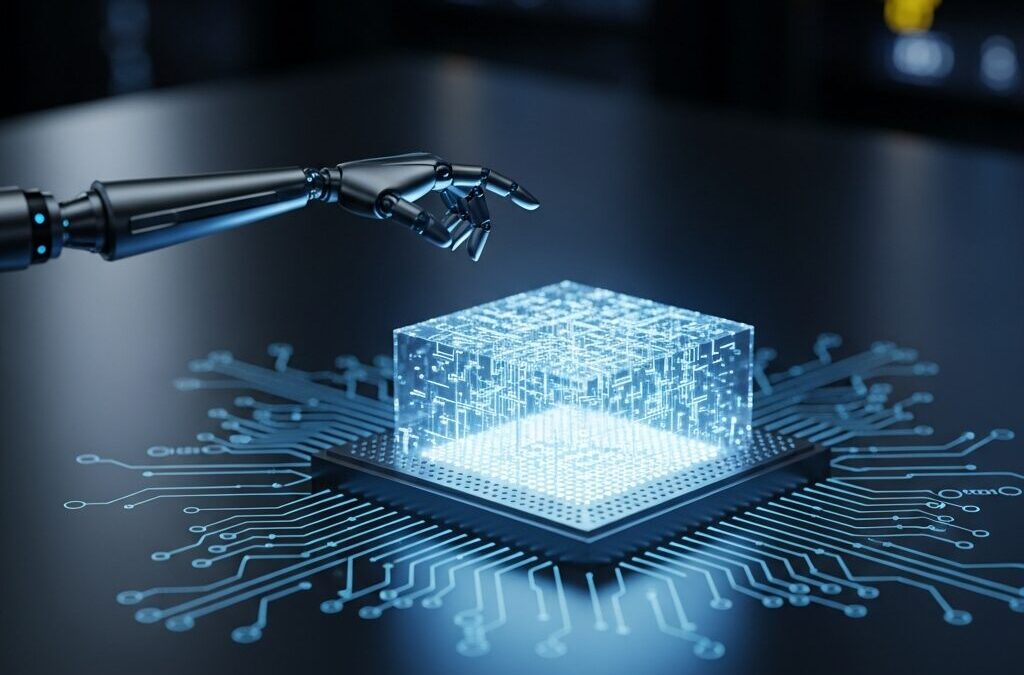生成AIの活用が当たり前になった今、多くの新規事業担当者が次の一手に悩んでいるのではないでしょうか。プロンプトを工夫すれば成果が出る時代は確かにありましたが、そのやり方に限界を感じ始めている方も少なくありません。
実際、AIは「うまく質問する道具」から、「自ら考え、行動し、成果を出す存在」へと急速に進化しています。2026年に向けて世界では、プロンプトエンジニアリングに代わり、AIエージェントを設計し、統率する力が競争優位の源泉になりつつあります。
本記事では、新規事業開発の責任者・推進者の視点から、なぜ今この変化が起きているのか、どのような技術的・市場的背景があるのかを整理します。さらに、日本企業の具体事例やデータを交えながら、AIエージェント時代に求められる新しいスキルと戦略を解説します。
読み終えたときには、生成AIを単なる効率化ツールとして使う発想から脱却し、自社の新規事業を次の成長フェーズへ導くための明確な視座を得られるはずです。
生成AIは第2幕へ:プロンプト中心時代の終わり
2022年のChatGPT公開以降、ビジネスの現場ではプロンプトエンジニアリングが一種の必須技能として急速に広まりました。どのような指示文を書けばAIが賢く振る舞うのか、その試行錯誤自体が競争力になる時代だったのは事実です。しかし2025年以降、この前提は大きく揺らぎ始めています。生成AIは「指示待ちの相手」から「自律的に動く存在」へと役割を変えつつあり、プロンプト中心の活用は限界を迎えています。
この転換を端的に示すのが、ガートナーの予測です。同社は、2026年までにエンタープライズアプリケーションの40%にエージェント型AIが組み込まれるとしています。ここで重要なのは、AIが単発の質問応答を行うのではなく、目標を与えられることで計画し、判断し、行動までを担う点です。つまり人間は細かな指示を書く役割から離れ、AIが働く前提条件そのものを設計する立場へ移行します。
| 観点 | 第1幕 | 第2幕 |
|---|---|---|
| AIとの関係 | 対話型 | 自律型 |
| 人間の役割 | 指示・修正 | 設計・監督 |
| 価値の源泉 | プロンプト技巧 | 文脈と仕組み |
マーケティングテクノロジー分野で知られるMark Ogne氏が「プロンプトエンジニアリングは戦略ではない」と述べているように、場当たり的な指示の工夫は再現性やスケールに乏しい手法です。新規事業のように複数の工程や不確実性を伴う領域では、検索、判断、修正をAI自身が循環的に行える設計が不可欠になります。
生成AIの第2幕とは、プロンプトを書く巧さを競う時代の終わりであり、AIが成果を出せる環境をいかに構築するかを競う時代の始まりです。この視点転換こそが、新規事業開発におけるAI活用を一過性のブームから、持続的な経営資産へと変えていきます。
なぜプロンプトエンジニアリングだけでは成果が出なくなったのか

生成AI活用の初期フェーズでは、巧みな指示文を書けば成果が出るという期待が広がっていました。しかし現在、多くの企業でプロンプトエンジニアリングだけでは業務成果が頭打ちになる現象が顕在化しています。その最大の理由は、プロンプトが本質的に「単発の対話」に最適化された技術だからです。
実務の現場で求められるのは、調査、判断、修正、再実行といった複数工程を含む連続的な仕事です。例えば市場調査一つ取っても、情報収集、信頼性の取捨選択、比較整理、示唆抽出が必要になります。これを毎回人がプロンプトで制御する形では、作業が属人化し、再現性もスケールもしません。
マーケティング分野の専門家であるMark Ogne氏が「プロンプトエンジニアリングは戦略ではない」と指摘しているように、プロンプトはあくまで即興的な操作手段に過ぎません。戦略的価値を生むには、AIが迷わず動ける前提条件そのものを設計する必要があります。
| 観点 | プロンプト中心 | 実務での限界 |
|---|---|---|
| タスク構造 | 単発指示 | 複雑業務に不向き |
| 再現性 | 個人依存 | 標準化できない |
| スケール | 人の操作量に比例 | 生産性が伸びない |
さらに問題なのは、プロンプト改善が人間の介在を前提としている点です。人が確認し、修正し続ける限り、AIは「補助ツール」の域を出ません。ガートナーが指摘するように、2026年に向けて企業システムは自律的にタスクを完遂するエージェント型へ移行すると予測されています。この流れの中で、逐一指示を書く行為そのものがボトルネックになります。
研究面でも差は明確です。arXivに掲載された複数の論文では、単一プロンプトによるゼロショット手法よりも、計画や自己修正を組み込んだエージェント的ワークフローの方が大幅に高い精度を示しています。これは「何と言わせるか」より「どう考えさせ、どう動かすか」が成果を左右することを意味します。
新規事業の現場では特に、仮説検証を高速に回す必要があります。その際、プロンプトの巧拙に依存するやり方は、学習速度も組織展開も遅くなります。成果が出なくなったのはAIの性能不足ではなく、プロンプトという操作単位が、事業の複雑性に追いつかなくなったことが本質的な原因です。
コンテキスト・エンジニアリングとAIエージェントの基本概念
生成AI活用の重心は、プロンプトを書く技術からコンテキストを設計する技術へと明確に移行しています。ここで言うコンテキスト・エンジニアリングとは、AIに与える一文の指示ではなく、AIが判断と行動を繰り返すための前提条件全体を構造的に埋め込む考え方です。データ、ルール、使える道具、禁止事項までを含んだ環境設計そのものが成果を左右します。
背景には、単発の質問応答では解けない業務課題の増加があります。ガートナーが指摘するように、企業システムの中でAIはチャットUIの裏側に溶け込み、複数ステップの業務を自律的に処理する存在へ変わりつつあります。このとき重要になるのが、AIが参照すべき社内データや判断基準を誤らせないための文脈制御です。
AIエージェントは「認識・推論・行動」を循環させる設計を持つAIシステムです。人間が毎回指示を出さなくても、目標だけを与えれば計画を立て、必要に応じて外部ツールやデータベースを使い、結果を自己修正しながら前に進みます。スタンフォード大学のAndrew Ng教授が示すエージェンティック・ワークフローは、この自律性を引き出す実践的な枠組みとして知られています。
| 観点 | 従来の生成AI | AIエージェント |
|---|---|---|
| 主な役割 | 質問への回答 | 目標達成の実行主体 |
| 人の関与 | 都度の指示と修正 | 初期設計と監督 |
| 成果の再現性 | 個人スキルに依存 | システム設計に依存 |
この違いは、新規事業開発において決定的です。例えば市場調査を行う場合、従来は担当者が調べ、まとめ、考察していましたが、エージェント型では「調査せよ」という目標の下で検索、比較、要約、表作成までを連続的に実行します。成果の質は、プロンプトの巧拙ではなく、どのデータにアクセスさせ、どの判断基準を与えたかで決まります。
マーケティング領域の専門家Mark Ogne氏が述べるように、プロンプトエンジニアリングは戦略ではありません。戦略となるのは、どのコンテキストをAIに預けるかを決める意思決定です。日本企業が強みとしてきた現場知や業務ルールを文脈として組み込めたとき、AIエージェントは単なる効率化ツールではなく、事業を前に進める実働部隊として機能し始めます。
エージェンティック・ワークフローを支える4つの設計パターン

エージェンティック・ワークフローを実務で成立させるためには、個々のAIモデルの性能以上に、どのような設計パターンで動かすかが決定的に重要です。スタンフォード大学のAndrew Ng教授が整理した4つの設計パターンは、すでに研究と実装の両面で事実上の標準になりつつあります。**重要なのは、これらが単独で価値を生むのではなく、組み合わせることで初めて業務品質を人間レベル、あるいはそれ以上に引き上げる点です。**
第一のパターンが反省です。これはAIが自らの出力を評価し、改善する工程を組み込む設計です。人間の仕事でもレビュー工程が品質を左右するように、AIでも同様の効果が確認されています。arXivに掲載された複数の研究では、単発生成に比べ、反省ループを組み込んだワークフローの方が論理的一貫性と正確性が大幅に向上することが示されています。**新規事業の企画書や市場分析のように、論点の抜け漏れが致命的になる業務ほど、この設計は不可欠です。**
第二が道具の使用です。LLMは知識を生成する存在ではなく、ツールを選択し実行する司令塔として設計することで真価を発揮します。Gartnerが指摘するように、企業アプリケーションに組み込まれるエージェントの多くは、検索、計算、社内データ参照といった外部機能と密接に連携します。**最新情報や数値の正確性が求められる新規事業検討では、AIに考えさせるのではなく、正しいデータを取りに行かせる設計が競争力を左右します。**
第三が計画です。これは複雑な目標をタスクに分解し、順序立てて実行させる設計パターンです。Andrew Ng教授は、巨大なモデルを待つよりも、計画能力を持たせたワークフローの方が実務性能は高いと述べています。実際、SocialMazeなどのベンチマークでは、計画と実行を分離したエージェントがゼロショット生成を大きく上回る結果を示しました。**新規事業では「何から着手すべきか」を誤ること自体がリスクであり、この設計はそのリスクを体系的に下げます。**
| 設計パターン | 主な役割 | 新規事業での価値 |
|---|---|---|
| 反省 | 自己評価と修正 | 企画・分析の品質安定化 |
| 道具の使用 | 外部データ・機能の実行 | 意思決定の根拠強化 |
| 計画 | タスク分解と順序制御 | 検討プロセスの再現性 |
| マルチエージェント | 役割分担と相互監視 | 疑似チームによる意思決定 |
第四がマルチエージェント協調です。異なる役割を持つエージェント同士を意図的に衝突させ、合意形成を行わせる設計です。これは人間の会議構造を模倣したもので、専門性と相互監視が同時に機能します。創薬や医療分野の研究でも、複数エージェントを連携させた方が精度と信頼性が高まることが示されています。**新規事業の仮説検証において、楽観と悲観の両視点を同時に走らせられる点は、人間以上に冷静な判断を可能にします。**
これら4つの設計パターンは、単なる技術論ではなく、AIを労働力として扱うための設計思想です。PwCの調査でも、エージェントを業務フローに組み込んだ企業の多くが、測定可能な生産性向上を実現しています。**新規事業開発においては、優秀なAIを探すことよりも、これらの設計パターンをどう組み合わせ、指揮するかが成否を分ける時代に入っています。**
2026年のAI市場予測とグローバル企業の動向
2026年のAI市場は、生成AIの実験フェーズを終え、企業インフラとして定着する転換点に入ります。最大の特徴は、チャット型AIから自律的に業務を遂行するエージェンティックAIへの重心移動です。Gartnerによれば、2026年までにエンタープライズアプリケーションの約40%にエージェントAIが組み込まれると予測されており、AIは「使うツール」ではなく「組み込まれている前提の機能」になります。
市場規模の観点では、IDCが示す予測が示唆的です。同社は2026年から2030年にかけて、アジア太平洋地域におけるデジタルビジネス由来の新規経済価値の50%をAIが牽引すると見ています。単体のAI製品売上ではなく、AIを前提に再設計された業務やサービス全体が価値創出の源泉になる点が重要です。
| 観点 | 2026年の予測 | 出典 |
|---|---|---|
| 企業アプリへの浸透 | 約40%がエージェントAIを標準搭載 | Gartner |
| 経済価値創出 | 新規デジタル価値の50%をAIが牽引 | IDC |
| 導入企業の成果 | 66%が測定可能な生産性向上を実感 | PwC |
この潮流を主導しているのが、グローバルテック企業です。Salesforceは金融や製造など業界特化型のAIエージェントを前面に押し出し、MicrosoftはCopilotを単なる支援AIから業務を横断的に動かすオーケストレーション基盤へ進化させています。これらに共通するのは、個別機能の高度化ではなく、業務全体をAIが自律的に回す設計思想です。
コンサルティングファームも動向を後押ししています。DeloitteやIBMは、AI投資の重点がモデル性能からエージェント指揮やガバナンス設計に移行すると分析しています。実際、PwCの調査では、すでにAIエージェントを導入している企業の約8割が関連予算の増額を計画しており、AIはコスト削減施策ではなく成長投資として扱われ始めています。
新規事業の文脈で見ると、この変化は大きな示唆を持ちます。グローバル企業はすでに、エージェントを前提にした新サービス設計や価格モデルの再構築に着手しています。人手を前提にした事業計画そのものが、2026年には競争力を失う可能性が高いため、市場予測とグローバル企業の動向を踏まえた視座の更新が不可欠です。
労働力不足が後押しする日本企業のAIエージェント活用
日本企業におけるAIエージェント活用を最も強く後押ししている要因は、技術トレンドそのものよりも、避けて通れない労働力不足です。IMFの分析によれば、日本は主要先進国の中でも生産年齢人口の減少スピードが速く、2030年に向けて人手不足が構造的に固定化すると指摘されています。この状況下では、単なる業務効率化ではなく、人が担ってきた役割そのものを代替・補完する存在としてAIエージェントが位置づけられています。
特に深刻なのは、ホワイトカラー領域の“静かな人手不足”です。新規事業開発、営業企画、調査・分析といった領域では、業務量は増え続ける一方で、経験者の採用は年々難しくなっています。ここで注目されているのが、調査、要約、資料作成、関係者調整といった一連の知的作業を自律的にこなすエージェントです。Gartnerが2026年までに企業アプリケーションの40%にエージェントAIが組み込まれると予測している背景には、こうした実務レベルの逼迫があります。
労働力不足がもたらす変化は、AIの導入目的そのものを変えています。従来は「人の生産性を10〜20%上げる」ことが期待値でしたが、現在は「そもそも人がいない業務をどう成立させるか」が論点です。ソフトバンクの孫正義氏が掲げる「社員1人あたり1,000体のAIエージェント」という構想は象徴的で、AIをツールではなくデジタルレイバー、すなわち仮想労働力として捉える発想を明確に示しています。
| 観点 | 従来のAI活用 | 労働力不足下のAIエージェント |
|---|---|---|
| 目的 | 業務効率化 | 労働力の補完・代替 |
| 人の関与 | 逐次指示・修正 | 目標設定と監督 |
| 成果指標 | 時間削減率 | 業務継続性・処理量 |
実務での導入が進む理由は明確です。例えば、新規事業部門では市場調査や競合分析を担う担当者が不足しがちですが、AIエージェントを使えば、24時間稼働で複数テーマを並列に処理できます。人がボトルネックにならないため、事業検討のスピード自体が変わります。IDCが指摘するように、2026年以降はAIが経済価値創出の中心になるとされており、その前提条件が「人手不足を前提とした業務設計」です。
重要なのは、AIエージェントが万能だからではなく、使わなければ業務が回らなくなる局面に日本企業が直面しているという点です。労働力不足という制約があるからこそ、エージェントは実験的な技術ではなく、事業を成立させるための必須インフラとして受け入れられ始めています。
日本企業の先行事例に学ぶエージェント活用のリアル
エージェント活用の議論を現実の事業に引き寄せるうえで、日本企業の先行事例は極めて示唆に富んでいます。共通しているのは、AIを「便利な回答装置」としてではなく、業務そのものを自律的に前進させる実行主体として設計している点です。構想倒れになりがちな生成AI活用に対し、明確な成果を生み出している企業は、導入前の問いの立て方が決定的に異なります。
例えばヤマト運輸では、需要予測AIと自動仕分け機を連動させ、現場オペレーションを直接制御するエージェント的な仕組みを構築しました。結果として配送効率は20〜30%向上し、営業利益率も約3%から5%超へ改善しています。ガートナーが指摘する「エージェンティックAIは業務フローに組み込まれて初めて価値を持つ」という見解を、数字で裏付けた事例だと言えます。
| 企業名 | エージェントの役割 | 主な成果 |
|---|---|---|
| ヤマト運輸 | 需要予測と配送・仕分けの自律最適化 | 配送効率20〜30%向上、利益率約80%改善 |
| 三菱UFJ銀行 | 顧客対応・行員業務の自律支援 | 行員の提案業務時間を創出、CX向上 |
| 日立製作所 | 熟練工の暗黙知を再現する保守支援 | 保守サービス期間約30%短縮 |
金融分野では三菱UFJ銀行がSalesforceのAgentforceを採用し、行員の指示を待たずに情報収集や次のアクション提案まで行うエージェントを導入しました。ここで重要なのは、自律性とガバナンスを同時に満たすプラットフォーム選択です。厳格な規制環境下でも実装できた点は、多くの新規事業担当者にとって現実的な指針になります。
製造業では日立製作所が、エスノグラフィ調査を通じて熟練工の判断プロセスを抽出し、RAGを用いた保守エージェントとして実装しました。これは単なるFAQ自動化ではなく、文脈を理解した意思決定支援であり、日本企業が強みとしてきた現場知をエージェントに移植した好例です。
これらの事例が示すリアルは明確です。成功している企業ほど、最新モデルの性能競争ではなく、「どの業務を、どこまで自律させるのか」という設計に時間をかけています。IDCが指摘するように、2026年に向けて価値を生むのはAIそのものではなく、エージェントをどう指揮するかです。その縮図が、すでに日本企業の現場で静かに形になり始めています。
新規事業担当者に求められる『エージェント指揮』という新スキル
新規事業担当者にとって、エージェント指揮は単なるAI活用スキルではありません。人間とAIエージェントを含む混成チームをどう設計し、どう動かすかという経営・事業設計そのものの能力です。従来のように自分が手を動かす、あるいはAIに逐一指示を出す立場から、目標と制約条件だけを与え、実行はエージェントに委ねる立場へと役割が変わります。
IBMやDeloitteが示す分析によれば、エージェント指揮の中核は「業務の再定義」にあります。既存業務をそのままAIに置き換えるのではなく、目的から逆算して業務を分解し、エージェントに任せる部分と人が担う部分を再設計します。ここで重要なのは、効率化だけを狙わないことです。人間は意思決定と責任、AIは探索・生成・実行という役割分担を明確にすることで、事業スピードが非連続に高まります。
例えば新規サービスの市場検証では、調査・仮説生成・検証設計・レポーティングといった工程を、複数のエージェントに並列で実行させることが可能です。Gartnerが指摘するように、エージェンティックAIは2026年までに企業アプリケーションの約40%に組み込まれる見通しであり、この前提に立てば、担当者が一人で全工程を管理する発想自体が時代遅れになります。
| 観点 | 従来型の担当者 | エージェント指揮型の担当者 |
|---|---|---|
| 役割 | 実務の主担当 | 目標設定と監督 |
| AIとの関係 | 補助ツール | 仮想メンバー |
| 成果の再現性 | 個人スキルに依存 | 設計次第で標準化 |
また、Eightfold.aiが指摘するように、エージェント指揮には「目利き力」も欠かせません。どのエージェントに、どのモデルやツールを割り当てるかで、成果とコストは大きく変わります。高性能モデルを一体使うより、用途特化したエージェントを複数連携させた方が、精度とスピードの両立が可能になるケースが増えています。
さらに見落とされがちなのがガバナンスです。IDCが警鐘を鳴らすように、管理されないエージェントはコスト爆発やセキュリティ事故を招きます。エージェント指揮とは、成果を最大化するだけでなく、暴走しない仕組みを同時に設計する責任を負うことでもあります。この視点を持てるかどうかが、新規事業の成否を分ける分岐点になります。
エージェント指揮を身につけた担当者は、人数や時間の制約から解放されます。少人数でも高速に仮説検証を回し、学習速度で競合を引き離すことが可能になります。これはスキルの進化であると同時に、新規事業開発そのものの進め方を変える構造的な変化だと言えます。
エージェント導入で無視できないリスクとガバナンスの論点
エージェント型AIは自律的に判断し行動するため、従来の生成AIとは異なるリスク構造を持ちます。便利さと引き換えに、統制を失えば経営リスクへ直結する点は、新規事業として導入する際に必ず正面から向き合うべき論点です。
特に無視できないのがセキュリティの変質です。Zscalerの脅威予測によれば、2026年に向けてAIエージェントは主要な攻撃対象になります。人ではなくエージェントがAPIを叩き、データを読み書きするため、巧妙なプロンプトインジェクションや、エージェント間通信の乗っ取りが現実的な攻撃ベクトルとして浮上しています。
「人のID管理」だけでは不十分で、「エージェントの振る舞い」を監視する発想への転換が求められます。これはGartnerやIBMが提唱するAIガバナンスの中心論点でもあり、行動ログの常時記録や異常検知を前提とした設計が不可欠です。
| リスク領域 | 具体的な問題 | ガバナンス上の論点 |
|---|---|---|
| セキュリティ | プロンプトインジェクション、権限逸脱 | 最小権限設計と行動監査 |
| コスト | 無限ループによるAPI費用増大 | 自動停止ルールと上限管理 |
| 組織統制 | 野良エージェントの増殖 | 全社的な台帳管理 |
IDCが警鐘を鳴らす「ゾンビエージェント」も見過ごせません。タスク完了後も稼働し続けるエージェントが、気づかぬうちにクラウドコストを膨張させる事例は、すでに海外企業で報告されています。これは技術の問題というより、責任者不在の運用設計というガバナンス不全の問題です。
そのため先進企業では、すべてのエージェントを登録・可視化する台帳を整備し、目的・権限・停止条件を明文化しています。人材や予算と同じく、エージェントも「経営資源」として管理する発想です。
もう一つ重要なのが期待値マネジメントです。Adecco Groupの調査では、日本ではAI導入による時間削減効果の実感が世界平均を下回っています。過度な期待が先行すると、現場でのPoC疲れを招き、結果的に新規事業そのものへの信頼を損ないます。
ガバナンスとはブレーキではなく、持続的にスピードを出すためのハンドルです。リスクを前提に設計されたエージェントこそが、新規事業をスケールさせる基盤になります。
2026年に向けた新規事業開発ロードマップの描き方
2026年に向けた新規事業開発ロードマップを描くうえで重要なのは、単なるスケジュール表ではなく、技術進化・組織能力・市場価値がどの順序で噛み合うかを設計することです。特に生成AIがエージェント化する現在、ロードマップの質が事業の成否を大きく左右します。
まず前提として押さえるべきは、2026年が「実験の年」ではなく「本格実装が前提となる年」だという点です。ガートナーは2026年までに企業向けアプリケーションの40%にエージェント型AIが組み込まれると予測しており、これは新規事業においてもAI前提設計が標準になることを意味します。
そのうえでロードマップは、時間軸ではなく成熟度軸で描くことが有効です。どの段階で何ができていれば次に進めるのかを明確にします。
| フェーズ | 主な目的 | 新規事業開発での到達状態 |
|---|---|---|
| 探索 | 機会の発見 | 顧客課題とAI適用余地が言語化されている |
| 設計 | 勝ち筋の仮説化 | エージェント前提の業務・価値設計が完成 |
| 検証 | 再現性の確認 | 限定領域でROIが数値で示されている |
| 拡張 | 事業化 | 人とAIが役割分担した運用が回っている |
探索フェーズでは、市場調査よりも業務分解が重要です。アンドリュー・ン氏が提唱するエージェンティック・ワークフローの考え方を参考に、顧客や自社の業務を認知・判断・実行に分解し、AIエージェントが担える単位を洗い出します。ここで曖昧なまま進むと、後工程でPoC止まりになります。
設計フェーズでは、プロンプトではなくコンテキストをどう埋め込むかが中心テーマになります。日立製作所の事例が示すように、マニュアルやデータだけでなく、判断基準や例外処理といった暗黙知をどこまで構造化できるかが、2026年以降の競争力を左右します。
検証フェーズではスピードよりも測定可能性を優先します。PwCの調査では、AIエージェント導入企業の66%が生産性向上を定量的に把握できているとされています。時間削減、意思決定精度、売上寄与など、必ず1つは経営指標に直結するKPIを置くことが不可欠です。
最後の拡張フェーズでは、ロードマップに組織変化を書き込みます。ソフトバンク孫正義氏が語るように、人は作業者ではなくエージェントの指揮者になります。評価制度や意思決定プロセスまで含めて描けて初めて、2026年に耐える新規事業ロードマップになります。
優れたロードマップとは、未来を当てるものではなく、変化に適応できる順序を定義するものです。その視点で描かれた計画だけが、エージェント時代の新規事業を現実の成果へ導きます。
参考文献
- MarTech:Prompt engineering is dead. Long live context engineering!
- Gartner(CodeZine):ガートナー、2026年までにエンタープライズアプリの40%にAIエージェント搭載と予想
- IDC:IDC FutureScape 2026 Predictions: AI to Drive 50% of New Economic Value from Digital Businesses in APJ
- IMF:The Impact of Aging and AI on Japan’s Labor Market: Challenges and Opportunities
- logmi Business:社員1人あたり1000本のAIを持つ未来へ ソフトバンク孫正義氏が明かす『千手観音プロジェクト』の挑戦
- 日立製作所:日立、数百の事例で獲得したOTナレッジの活用手法によりお客さまのDXを加速