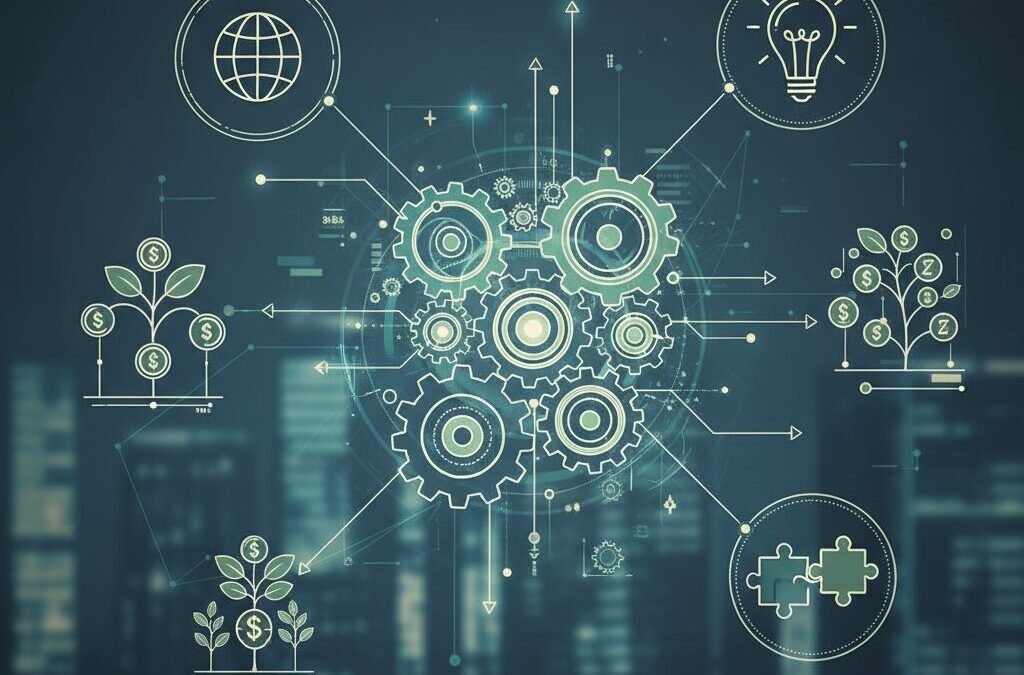ESGや脱炭素が企業価値を高めると言われた時代は、すでに次の局面へ進んでいます。近年、環境配慮をうたう表現が規制当局の監視対象となり、実態を伴わない取り組みは事業リスクそのものになりました。新規事業開発の現場では、「環境に良さそう」ではもはや評価されず、科学的根拠と収益性を両立した実装力が問われています。
一方で、欧州の規制強化、日本のGX政策、グローバル企業によるサプライチェーン圧力は、見方を変えれば巨大な市場再編のシグナルでもあります。鉄鋼やエネルギー、素材といった削減困難領域では、ディープテックへの投資と事業化が静かに加速しています。さらに、炭素除去や自然資本、気候変動への適応といった新領域も、次の成長軸として浮上しています。
本記事では、新規事業開発を担う方に向けて、グリーンウォッシュ終焉後のクライメート・テックの現在地を整理し、規制・投資・技術・市場がどのようにつながっているのかを解説します。読み終えたとき、自社がどこで勝負すべきか、次の一手が具体的に見えることを目指します。
グリーンウォッシュが許されない時代への転換
2020年代前半に広がったESGブームは、企業にとって環境配慮を「語る」こと自体が価値になる時代でした。しかし2024年以降、その前提は大きく崩れています。**いま企業が直面しているのは、環境への取り組みを主張する自由と引き換えに、科学的根拠を示す義務を負う時代**への転換です。
欧州委員会の調査によれば、市場に出回る環境主張のうち53.3%が曖昧または誤解を招く表現で、40%は裏付けとなる証拠を欠いていました。こうした実態を背景に、EUではグリーンクレーム指令が進められ、「エコ」「カーボンニュートラル」といった言葉の使用に、ライフサイクル全体での定量的証明と第三者検証が求められる方向へ進んでいます。
この流れは単なる表示規制ではありません。**マーケティング表現そのものが、法的・財務的リスクを伴う経営判断になった**という点に本質があります。実際、コカ・コーラは「100%リサイクル」との表現が誤解を招くとして是正を求められ、ユニリーバも環境配慮の主張が不十分だとして各国当局の調査対象となりました。
| 従来 | 現在 | 企業への影響 |
|---|---|---|
| イメージ重視の環境訴求 | 証拠重視の環境主張 | データ整備・検証コストが増大 |
| オフセット中心 | 実排出削減の優先 | 設備投資や調達戦略に直結 |
| 自主的取り組み | 規制・監視下の対応 | 不備は法的リスクに |
特に象徴的なのが、ボランタリー炭素市場で起きた信頼崩壊です。英ガーディアン紙などの共同調査により、最大手認証機関Verraが認証した森林クレジットの9割以上が実質的な削減効果を持たない可能性が指摘されました。これにより、安価なオフセットで「実質ゼロ」を謳う手法は、グリーンウォッシュの代表例として扱われるようになっています。
その結果、市場では明確な選別が始まりました。科学的に永続性が高いとされるバイオ炭やDACなどの「除去系」技術に資金が集中し、MicrosoftやGoogleといった企業は、森林系クレジットから距離を置く姿勢を明確にしています。**信頼できる脱炭素価値には、明確な価格が付き始めた**のです。
新規事業開発の観点では、この変化は脅威であると同時に機会でもあります。曖昧な主張に依存した競合が淘汰される一方、データと実装に裏打ちされた技術やサービスは、規制そのものを参入障壁として活用できます。**グリーンウォッシュが許されない時代とは、言い換えれば「本物だけが残る市場」への移行期**であり、その現実を直視する企業こそが次の成長機会を掴むことになります。
欧州グリーンクレーム規制が事業戦略に与える影響

欧州グリーンクレーム規制は、単なる広告表現のルール変更にとどまらず、企業の事業戦略そのものに直接的な影響を与えています。欧州委員会の調査によれば、企業の環境主張の53.3%が曖昧または根拠不十分と判断されており、**「言えば評価される」時代は完全に終わった**と言えます。
この規制下では、「エコ」「グリーン」「カーボンニュートラル」といった言葉を使うために、製品ライフサイクル全体に基づくデータ提示と第三者検証が求められます。結果として、マーケティング主導で環境価値を演出するモデルから、**実装と証明を前提にした事業設計**への転換が不可避となっています。
特に事業戦略上のインパクトが大きいのは、コスト構造と競争優位性の再定義です。環境主張を行うための調査、LCA算定、検証対応には追加コストが発生しますが、DNVなどの第三者機関の分析によれば、これらを早期に内製化した企業ほど、規制対応を参入障壁として活用できています。
| 戦略領域 | 従来 | 規制後の変化 |
|---|---|---|
| 環境訴求 | 広告・PR中心 | データと検証が前提 |
| 投資判断 | 短期ROI重視 | 長期CAPEXと証明力重視 |
| 競争軸 | ブランドイメージ | 透明性と再現性 |
実際、コカ・コーラやユニリーバが是正勧告を受けた事例は、グローバル企業であっても例外ではないことを示しています。**規制対応が遅れた場合、ブランド毀損だけでなく市場退出リスクに直結する**点は、新規事業にとって極めて重要な示唆です。
新規事業開発の視点では、規制を前提にした価値提案設計が鍵となります。具体的には、環境データ取得や検証プロセスそのものをプロダクトやサービスに組み込み、顧客の規制対応コストを下げる発想です。Sidley Austin法律事務所の指摘によれば、こうした設計は顧客ロイヤルティを高め、価格競争からの脱却にも寄与します。
欧州グリーンクレーム規制は、企業にとって負担であると同時に、**信頼を競争力に変換できる企業だけが選別される市場環境**を生み出しています。この現実を直視し、事業戦略に組み込めるかどうかが、今後の成長を左右します。
ボランタリー炭素市場の信頼崩壊と除去技術の台頭
ボランタリー炭素市場は、かつて企業の気候変動対策を支える柔軟な仕組みとして急成長しましたが、2023年以降、その信頼性は大きく揺らぎました。転機となったのが、英ガーディアン紙などによる調査報道で、最大手認証機関Verraが認証した森林保全クレジットの90%以上が実質的な削減効果を持たない可能性が指摘されたことです。排出削減を「したことにする」クレジットが市場に大量供給されていたという事実は、企業のESG戦略そのものを直撃しました。
問題の本質は、回避系クレジットに内在する構造的欠陥です。森林破壊が起きていたはずだという仮定を過大に設定することで、実際には追加性のない削減量が計上されていました。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの分析でも、こうしたベースライン操作は制度設計上避けがたいと指摘されています。この結果、クレジット価格は下落し、多くの企業が購入を見直す事態となりました。
この空白を埋める形で急速に存在感を高めているのが、二酸化炭素除去、いわゆるCDRです。CDRは大気中のCO2を物理的に回収し、長期間固定するため、計算上の相殺ではなく実体のあるネガティブエミッションを提供します。世界経済フォーラムも、ネットゼロ達成には削減と並行して除去が不可欠だと整理しています。
| 区分 | 代表例 | 信頼性の評価 | コスト水準 |
|---|---|---|---|
| 回避系 | REDD+ | 低〜中 | 低 |
| 除去系 | バイオ炭 | 高 | 中 |
| 除去系 | DAC | 非常に高 | 高 |
特にバイオ炭は、CDR市場で突出した成長を示しています。CDR.fyiによれば、2022年から2025年上半期にかけて300万トン超の契約が成立し、MicrosoftやGoogleといった企業が主要な買い手となっています。農地改良という副次的価値もあり、コストと信頼性のバランスが取れた除去技術として評価されています。
- 安価な回避系クレジットはブランドリスクを高めやすい
- 除去系は高コストだが規制耐性と説明責任に強い
新規事業の視点では、この二極化は重要な示唆を持ちます。炭素市場はもはや数量勝負ではなく、科学的裏付けと永続性が価格を決める市場へ変わりました。どのクレジットを選ぶかは、企業の本気度を示す投資判断であり、信頼を失った市場の上に新たな技術とビジネスが再構築されつつあります。
日本のGX戦略と150兆円投資が生む新規事業機会

日本のGX戦略は、環境政策という枠を超え、国家主導で市場そのものを創出する産業政策として設計されています。今後10年間で官民合わせて150兆円という投資規模は、日本のGDPの約4分の1に相当し、新規事業開発にとっては極めて異例の追い風です。重要なのは、この資金が補助金のばらまきではなく、将来のカーボンプライシング収入を見据えた金融設計に基づいている点です。
経済産業省のGX構想によれば、政府はGX経済移行債を通じて先行的に約20兆円を投じ、民間投資130兆円を呼び込む仕組みを構築しています。これにより、技術の社会実装フェーズに入った分野に、長期・大規模・継続的な需要が生まれることが制度的に担保されます。
| 投資領域 | 想定される事業機会 | 新規事業の切り口 |
|---|---|---|
| エネルギー転換 | 水素・アンモニア、洋上風力 | 供給網構築、運用最適化、周辺サービス |
| 産業プロセス | 鉄鋼・化学・セメント | 設備転換支援、プロセス制御、データ活用 |
| 需要側・省エネ | 建築、モビリティ、蓄電池 | B2Bソリューション、金融連動モデル |
特に新規事業の観点で見逃せないのが、GX-ETSの本格稼働を見据えた「準義務市場」の存在です。2026年以降、多排出企業は排出量削減かクレジット調達を迫られ、脱炭素対応そのものが事業継続の前提条件になります。野村総合研究所やICAPの分析によれば、日本のGX-ETSは当初価格を抑えつつも、対象範囲と参加企業を段階的に拡大する設計であり、市場規模は時間とともに確実に拡大すると見込まれています。
この構造は、新規事業に二つの機会をもたらします。一つは、排出削減を直接実現する技術・サービスです。もう一つは、GX対応を円滑に進めるための周辺事業であり、計測・報告・金融・人材といった分野に需要が波及します。
- GX投資を前提とした設備更新・リース・アズアサービス化
- GX-ETSやJ-クレジット対応を組み込んだ業務支援
- 地方産業と結びつく分散型GXプロジェクト
IEAやLSEGの分析でも、日本のGXはアジア全体への波及を視野に入れたモデルと位置付けられています。国内市場で実装された技術や事業モデルは、そのままアジアの脱炭素需要に展開可能です。国内GXは実験場であり、海外展開の足がかりでもあります。
新規事業開発において重要なのは、補助金獲得をゴールにしないことです。GX戦略は、規制・金融・需要を同時に動かす長期シナリオです。その時間軸を理解し、制度が生む“確定需要”にどう入り込むかを設計できるかどうかが、成否を分けます。
GX-ETSと国内クレジット市場のリアルな価格感
GX-ETSの議論で見落とされがちなのが、国内クレジット市場における「実際の価格感」です。制度設計や理念ではなく、企業が現場で直面しているのは、1トンのCO2削減価値にいくら支払うのかという極めて生々しい判断です。東京証券取引所に開設されたカーボン・クレジット市場は、そのリアルを可視化する装置として機能し始めています。
JPXが公表している取引データによれば、J-クレジットの価格は一様ではなく、クレジットの「質」によって明確な差が生じています。Scope2削減に直結する再エネ由来クレジットは取引量が多く、比較的安定した価格帯を形成しています。一方で、森林吸収系やブルーカーボンのようなストーリー性と希少性を持つクレジットは、高値でも成立する状況です。
| クレジット種別 | 価格帯(円/トン) | 市場での評価軸 |
|---|---|---|
| 再エネ電力 | 約2,000〜4,000 | 実務的・流動性重視 |
| 省エネ | 約1,500〜2,000 | 供給過多で低評価 |
| 森林吸収 | 約6,000〜9,000 | 希少性・物語性 |
この価格差は偶然ではありません。IEEJや市場関係者の分析によれば、企業は「とりあえず安く埋める」フェーズから、「説明可能で監査に耐える削減価値」を求めるフェーズへ移行しつつあります。GX-ETSが2026年以降に本格化すれば、目標未達がより明確に評価されるため、クレジットの品質リスクがそのまま経営リスクになります。
また、日本のGX-ETSにおける炭素価格は、欧州EU ETSのように急騰する設計ではないとされています。三菱総研や野村総研の試算では、当初は数千円規模から始まる可能性が高く、国際的な脱炭素コストと比べると低水準です。しかし逆に言えば、この水準こそが国内クレジット価格のアンカーとなり、企業の「内製削減」と「市場調達」の判断基準になります。
新規事業の観点では、この価格感は重要な示唆を与えます。数百円の差ではなく、数千円から1万円規模で評価される削減価値をどう生み出すか。森林、農業、バイオ炭、ブルーカーボンなど、地域資源と結びついたクレジットが注目される背景には、GX-ETSという制度市場で通用する価格帯が、すでに現実の数字として共有され始めている事実があります。
ディープテックが直面する死の谷と突破の条件
ディープテックが直面する最大の構造課題が「死の谷」です。これは研究開発段階で技術的な有効性が示されても、商業規模に到達するまでに資金・時間・需要のいずれもが枯渇しやすい空白地帯を指します。特にクライメート・テックのような物理的実装を伴う領域では、この谷が深く長くなりがちです。
国際エネルギー機関によれば、鉄鋼や化学、セメントといった削減困難セクターの脱炭素技術は、商用化までに10年以上を要するケースが一般的とされています。**開発期間の長期化は、VCファンドの投資回収期間(7〜10年)と根本的に相性が悪い**という問題を生みます。
| 段階 | 主な資金源 | 典型的なリスク |
|---|---|---|
| 研究・実証 | 補助金・助成金 | 技術は成立するが需要が未検証 |
| スケールアップ | VC・CVC | 設備投資が急増し資金不足 |
| 商業化 | 融資・プロジェクトファイナンス | オフテイク不足・価格競争 |
この谷をさらに深くしているのが、規制と市場の同時進行です。欧州のグリーンクレーム指令や炭素市場の信頼性危機により、未成熟な技術や実証データの乏しいプロジェクトは、以前にも増して厳しい検証を受けるようになりました。**技術的に正しくても、規制適合と第三者検証を通過できなければ市場に出られない**のです。
一方で、この死の谷を突破する条件も徐々に明確になっています。第一に、単独での商業化を目指さないことです。PowerXが金融機関から大規模融資を引き出せた背景には、有形資産としての工場と、商社・大企業との提携がありました。これは市場側にとって、需要と継続性を担保するシグナルになります。
- 長期オフテイク契約による需要の可視化
- 商社やインフラ企業とのJV構造
- 補助金とデットを組み合わせた資金設計
第二に、プレミアム市場を初期ターゲットにする戦略です。CDR市場でバイオ炭が支持されているのは、コストの安さだけでなく、科学的永続性という明確な価値があるためです。MicrosoftやGoogleといった買い手は、量より質を重視し、初期段階から高単価での購入に応じています。
第三に、国家戦略との接続です。日本のGX戦略のように、150兆円規模の官民投資が予定されている分野では、技術そのものよりも「政策の射程に入っているか」が成否を分けます。成長志向型カーボンプライシングやGX-ETSの導入は、将来の価格シグナルを先読みできる事業者に有利に働きます。
ディープテックの死の谷は、単なる資金不足ではなく、時間軸・規制・市場設計のミスマッチから生じます。**それらを統合的に設計できた企業だけが、長い冬を越えて産業標準へと成長していく**のです。
水素・アンモニア分野で存在感を増す総合商社の役割
水素・アンモニア分野で日本の総合商社が存在感を増している背景には、単なる投資家や仲介者ではない、独特の産業的役割があります。**最大の特徴は、技術・資本・需要を束ね、長期の不確実性を引き受ける「リスク吸収装置」として機能している点**です。
水素やアンモニアは、製造から輸送、利用までの全体最適がなければ事業として成立しません。IEAや経済産業省の資料によれば、現在の低炭素水素コストは目標水準の数倍に達しており、単一企業での事業化は困難です。ここで商社は、自らのバランスシートを活用し、複数国・複数企業をまたぐサプライチェーンを設計します。
具体的には、上流の資源国での製造投資、中流の輸送・貯蔵インフラ、下流のオフテイク契約を同時並行で組み上げます。三菱商事が米国で低炭素アンモニア製造に参画し、日本の発電事業者への供給を視野に入れている事例は、その典型です。ExxonMobilのようなメジャー企業との提携は、技術信頼性とスケール確保の両立を可能にしています。
また、三井物産がPETRONASと進めるCCS連携は、従来の資源開発で培った地質評価や長期操業の知見を、水素・アンモニア時代に転用する好例です。**CCSを含めた低炭素認証がなければ、欧州を中心とする規制環境下で燃料としての競争力を失う**ため、商社は燃料そのものだけでなく「環境価値」まで含めて設計しています。
| 機能 | 商社の役割 | 事業的な意味 |
|---|---|---|
| 資本 | 自己資本による長期投資 | 初期赤字を許容しスケール化を可能に |
| 需要創出 | 電力・鉄鋼とのオフテイク契約 | 価格・数量の不確実性を低減 |
| 国際交渉 | 産油国・新興国政府との関係構築 | 安定供給と制度リスクの回避 |
さらに重要なのは、スタートアップや技術ベンダーに対する「実装の場」を提供している点です。住友商事が高効率水電解技術を持つH2Proに出資しているように、商社は技術を単に評価するのではなく、自社プロジェクトに組み込み、実証から商用化まで導く役割を担います。これは、VC主導では越えられないディープテックの死の谷を埋める動きだと専門家も指摘しています。
水素・アンモニア事業は、短期収益では測れません。**規制、補助金、カーボンプライシングを前提にした10年単位の時間軸で初めて合理性を持つ産業**です。その長い時間と巨大な不確実性を引き受けられる主体として、総合商社は今後も日本のGX戦略の中核に位置づけられていくと考えられます。
日本発クライメート・テックスタートアップの現在地
日本発のクライメート・テックスタートアップは、理想先行の実験段階を抜け、産業実装と資本市場の現実に直面するフェーズに入っています。欧米と比べて立ち上がりは緩やかでしたが、その分、重厚長大型産業と結びついた独自の進化を遂げつつあります。
象徴的なのが、素材・エネルギー・燃料といった「物理領域」に挑むディープテック企業です。Spiberは発酵由来の構造タンパク質でアパレルの脱石油を目指し、ユーグレナは微細藻類を起点にSAFやバイオ燃料の商業化へ踏み込みました。これらは華やかなSaaS型とは異なり、量産化までに10年以上と巨額のCAPEXを要する点が特徴です。
一方で、近年は資金調達の質にも変化が見られます。PowerXは蓄電池製造というハードアセットを武器に、VCだけでなく金融機関からのデットファイナンスを引き出しました。これは、日本のスタートアップが「成長物語」だけでなく、需要の確実性と資産価値を示せば銀行融資を活用できる段階に来たことを示唆しています。
ただし課題も明確です。経済産業省や有識者の分析によれば、日本のディープテックは「死の谷」が深く、単独でのスケールアップは困難とされています。そのため近年は、総合商社やエネルギー大手とのJV、オフテイク契約を前提とした成長戦略が主流になりつつあります。
以下は、日本発スタートアップに共通する現在の特徴です。
- 対象市場は国内完結ではなく、最初からグローバル産業を想定
- 技術優位性よりも、量産・供給体制の構築力が評価軸
- VC資金と事業会社・金融機関資金のハイブリッド化
日本発クライメート・テックは爆発的成長よりも、時間をかけて産業に組み込まれるモデルを選び始めています。これは派手さに欠ける一方で、GX政策やサプライチェーン規制と噛み合ったときに大きな果実を生むポジションでもあります。今はまさに、その耐久戦の真っただ中にあると言えるでしょう。
Scope3削減が中小企業と新規事業にもたらす圧力
Scope 3削減は、もはや一部の先進企業だけの課題ではなく、中小企業や新規事業にとっても避けられない外部圧力となっています。特にグローバル企業が掲げるサプライチェーン全体での脱炭素目標は、取引条件そのものを変えつつあり、対応できない企業は市場から静かに排除されるリスクを抱えています。
**Scope 3とは、原材料調達、物流、使用、廃棄など自社の直接管理外で発生する排出量**を指します。CDPやGHGプロトコルによれば、多くの製造業では全排出量の7〜9割をScope 3が占めるとされています。つまり、大企業がネットゼロを本気で達成しようとすれば、取引先である中小企業にも削減を求めざるを得ない構造です。
| 圧力の発信源 | 具体的要求 | 中小企業への影響 |
|---|---|---|
| グローバル企業 | 排出量データ提出、再エネ利用 | 取引継続の前提条件化 |
| 規制・基準 | Scope 3開示、算定精度 | 管理コスト・人材不足 |
| 金融機関 | 脱炭素計画の有無 | 融資条件・金利への影響 |
Appleがサプライヤーに100%再生可能エネルギーを求めている事例は象徴的です。日本企業でも、対応のために特定ラインを再エネ化したケースが報告されています。一方、Toyotaのように前年比3〜5%の改善を段階的に求めるアプローチもありますが、いずれにしても**環境対応はQCDに並ぶ評価軸**になっています。
中小企業にとって厳しいのは、削減そのもの以上に「見える化」と「説明責任」です。帝国データバンクの調査でも、脱炭素に関心はあっても、コスト負担や算定ノウハウ不足が障壁とされています。このギャップを埋める存在として、AsueneやZeroboardなどの炭素会計SaaSが急速に普及しています。
- 請求書や電力データから排出量を自動算定
- 取引先からの質問に即応できるレポート生成
- 金融機関や自治体支援と連動
新規事業の視点で見ると、この圧力は脅威であると同時に機会でもあります。Scope 3対応を前提にした省エネ設備、再エネ調達支援、データ管理サービスは、顧客の「やらざるを得ない課題」に直結します。**削減を支援する側に回れるかどうか**が、これからの事業機会を左右します。
重要なのは、完璧な削減よりも「測り、説明し、改善する」姿勢です。国際機関や大企業が重視しているのは一貫性と透明性であり、小さな改善でも継続的に示せる企業は評価されます。Scope 3削減の圧力は、中小企業と新規事業に経営の成熟度そのものを問う試金石となっています。
適応とネイチャー・ポジティブが開く次の市場
脱炭素の議論が成熟期に入る中で、次の成長市場として浮上しているのが気候変動への適応とネイチャー・ポジティブの実装領域です。これは排出削減の代替ではなく、既に顕在化している被害やリスクに対応し、同時に自然資本を価値へと転換する現実的な市場だと言えます。
国連環境計画によれば、世界の気候適応市場は2030年までに年間3,000億ドル規模に達すると推計されています。一方で実際の投資額は必要水準を大きく下回っており、このギャップそのものが新規事業の余地を示しています。特に日本は災害対応、インフラ管理、農業技術といった分野で実装知を蓄積しており、輸出可能な競争力を持っています。
適応ビジネスの特徴は、顧客が企業や自治体、インフラ事業者といった明確なB2B主体である点です。例えば、AIを用いた災害可視化SaaSは、被害を未然に防ぐことで保険コストや復旧費用を削減します。内閣府や総務省の防災白書でも、リアルタイム情報共有の重要性が強調されており、公共調達と民間需要が重なり合う市場構造が形成されています。
一方、ネイチャー・ポジティブ領域では、生物多様性や自然資本を「測れる価値」として扱う動きが加速しています。OECDは、生物多様性クレジットが将来的に炭素市場と並ぶ補完的市場になる可能性を指摘しています。日本でもTNFDの早期採用企業が多く、開示対応を起点に具体的な投資・事業化へ進む企業が増えています。
| 領域 | 主な顧客 | 事業価値の源泉 |
|---|---|---|
| 気候適応 | 自治体・インフラ企業 | 被害回避によるコスト削減 |
| ネイチャー・ポジティブ | グローバル企業 | 自然資本の可視化と信用力 |
新規事業開発の視点では、ここで重要なのは「技術単体」ではなく制度・金融・データと組み合わせた市場設計です。適応指標の標準化や、生物多様性価値の認証スキームと連動できる事業は、参入障壁が高く、長期的な競争優位を築きやすくなります。
緩和策の限界が意識される今、適応とネイチャー・ポジティブは周縁的テーマではありません。既に始まっている現実の変化に応え、経済合理性を伴って成長する、次の本命市場として位置付けるべき段階に入っています。